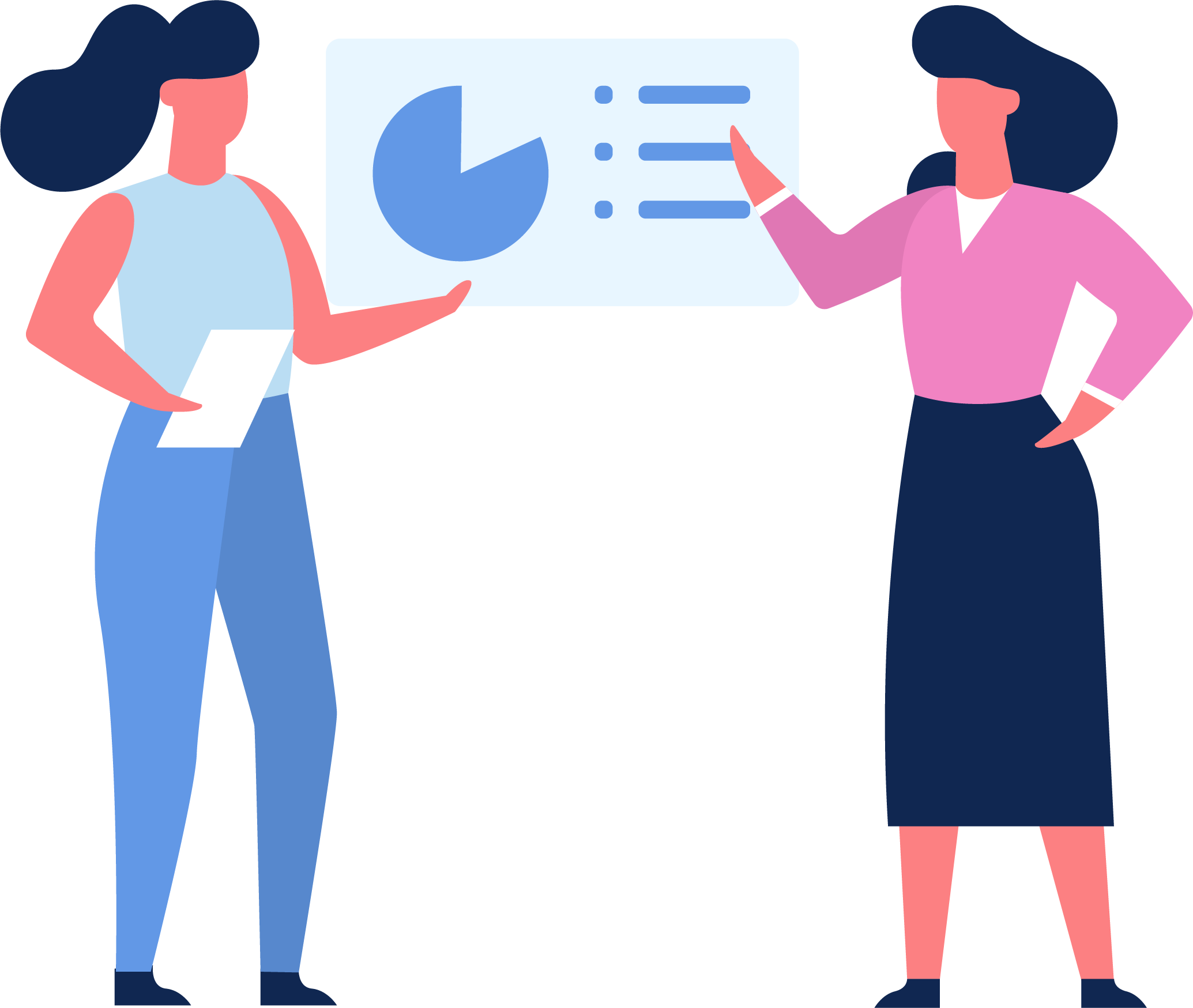不動産特定共同事業法とは
不動産を小口化し投資商品として販売する「不動産特定共同事業法」の改正法が2017年12月1日に施行されました。
改正により、地方の小規模不動産業者が不動産証券化を活用して再生事業に参入する機会が生まれました。
不動産特定共同事業法は、平成6年6月に制定された法律です。この「不動産特定共同事業」というのは、小口の資金を集めてその資金を元手に不動産投資を行い、そこから得られた収益を投資金額に応じて配分するという仕組みになっている不動産事業のことです。
不動産特定共同事業とは、「複数の投資家からの出資により不動産を取得し、不動産を運営して得た収益を投資家に分配する仕組み」のことです。
貸金業とは異なり物件情報の開示が可能なため、物件を見ながら投資できるというのが最大のメリットです。